社外取締役と機関投資家との対話
社外取締役と機関投資家との対話
ステークホルダーの皆さまからの多様な意見を取り入れ、ガバナンスの質をさらに高めて
まいります。
Daigasグループでは、ガバナンスの強化に向けた取り組みの一環として、社外取締役と投資家との意見交換の場を設けています。2025年3月、社外取締役2名と機関投資家の皆さまで、多岐にわたるテーマについて率直かつ実りある対話を行いました。

取締役(社外)
来島 達夫
2016年から約3年間、西日本旅客鉄道(株)(JR西日本)の代表取締役社長を務め、同社の経営改革を推進。
2020年6月に当社の社外取締役に就任。
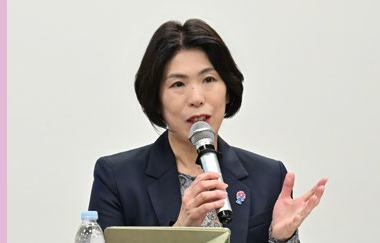
監査等委員である取締役(社外)
梨岡 英理子
公認会計士・税理士として豊富な経験を有し、
環境管理会計研究所の代表取締役を務めるなど、
環境会計の専門家として活躍。
2022年6月に当社の社外監査役に就任、2024年6月より監査等委員である取締役に就任。
PBR向上に向けて
ROE8%の達成が優先課題であり、従来の規制事業に捉われず
成長を追求していく姿勢が重要です。
Q. 東証のPBR改善要請に対する現状の取り組みをどのように評価していますか。
来島現在、大阪ガスのPBRは0.8台にとどまっており、執行側はPBR1倍超の実現に向けて覚悟を持って取り組んでいると受け止めています。
PBR向上には、従来の規制事業であるガス事業にいつまでも依存するのではなく、事業環境の変化に対応しながら成長を追求する姿勢が求められます。
PBRはROEとPERの掛け算であり、まずはROEの引き上げが不可欠です。中期経営計画2026で掲げたROE8%の達成を優先課題とし、安定的にそれを上回る水準を目指すことが必要と考えます。
資本効率向上の取り組み
バランスシートを意識した経営管理の徹底を図り、
組織全体の収益力向上を目指すことでご期待に応えていきます。
Q. 資本効率向上に対する取り組みとして重要な点は何だと思われますか。
来島当社グループは、海外エネルギー事業やライフ&ビジネスソリューション(LBS)事業などの成長により、キャッシュ・フローや事業ポートフォリオを強化してきたこと等を踏まえ、自己資本比率の最適水準を50%から45%以上へと引き下げました。インフラ企業として長期的な設備投資が求められるなか、最適な資本構成は「財務健全性」と「資本効率向上」のバランスの観点を踏まえて、柔軟に決定すべきものと考えています。
取り組みにおいては、バランスシートを意識した投資判断や経営管理の徹底と、組織全体の収益力向上が重要です。当社グループは2021年度からROIC経営を導入し、2026年度のROIC5%目標に向けて、各事業ユニットでKPIを設定し業績変動の兆候を早期に把握、改善行動に結びつける体制を構築しています。その際に、有利子負債や株主資本コストの水準を検討し、WACCを低く抑えるという観点が不可欠だと考えています。
Q. 同じインフラ事業である鉄道会社のように、自己資本比率を3割などに減らすことで企業価値向上を図るべきと考えていますか。
来島当社グループは2017年のガス小売全面自由化、加えてカーボンニュートラルへの対応など、エネルギー業界特有の構造的リスクを抱えています。これらを踏まえると、他社との自己資本比率の差は業態の違いだけではなく、リスク認識の違いとして妥当であると考えます。
当社グループは2026年度のROIC5%を目指していますが、国内エネルギー事業のROICの低さが気になります。鉄道会社における鉄道事業も同様で、全体のROICを引き上げるには、やはり祖業の収益性向上が不可欠だと考えています。
また企業価値向上のためには、バランスシート全体をどう設計するかが重要ですが、「自己資本比率45%以上」は現時点の目安であり、今後さらに見直す可能性もあるでしょう。鉄道会社との比較は参考になりますが、同じ水準を目指すことが最適かどうかは慎重に判断すべきと考えます。
Q. ROICの観点で、ガス事業の一部やその資産を切り離すことについてはどう思われますか。
来島ただ計算上のROICを良くするためにガス事業の一部の資産を切り離したりすることは本質的ではありません。当社グループの使命としてガス事業は維持する前提のもと、ROICをいかに高めるかに取り組むべきだと考えています。単に「ROIC経営」と言うだけでは不十分であり、私も社外取締役の責務として利益構造の理解をより深め、ROICの分子、分母それぞれの改善方法を議論し、次の成長を目指していきたいと思います。
気候変動に対する取り組み
積極的な情報開示と対話により、先進的な取り組みに対する
社会の理解を促進する役割があると感じています。
Q. 気候変動に対する取り組みをどのように評価していますか。
梨岡私は環境会計などに長く携わってきたこともあり、気候変動という社会課題にどう向き合うかは重要なテーマだと捉えています。
当社グループは、2025年2月に「エネルギートランジション2050」を公表し、e-メタンの開発やCCUS(CO2の回収・有効利用・貯留)など、現実的かつ戦略的な対応を進めています。エネルギー事業者として「S+3E(安全・環境・経済・安定供給)」の観点を大切にし、「環境のために全てを犠牲にする」のではなく、「持続可能な社会の実現に向けたバランスの取れた対応」が重要だと考えます。
一方でe-メタンやCCUSは、太陽光発電や風力発電に比べて知名度が低く、十分にその存在を知られていません。だからこそ、当社グループには積極的な情報開示と対話によってステークホルダーの理解を深める役割があると感じています。
また、私は「CO2削減貢献量」の考え方には合理性があると考えています。環境に配慮した製品を先行して市場に出した企業にとって、その製品の生産量を拡大すれば自社のCO2排出量は増えますが、社会全体の排出削減に寄与しているという事実は正当に評価されるべきです。この考えは、私がかかわってきた環境会計における「利益貢献効果」や「リスク回避効果」とも一致しています。
もちろん、計算方法の透明性や信頼性の確保が必要であり、今後はより多くの企業が削減貢献量を開示し、第三者検証やルールの整備による公正な基準の構築が求められます。当社グループとしても国際的な議論の動向を注視しながら、企業の取り組みが適切に評価される仕組みづくりに貢献していきたいと考えています。
Q. カーボンプライシングの導入を見据えると、今後はCO2削減目標についても、量だけでなく金額ベースでの開示が求められるのではないでしょうか。特にエネルギー業界での動きについて、ご意見を伺えますか。
梨岡カーボンプライシングは、企業のなかで「環境投資は利益に貢献しない」との見方に対する反証として始まったもので、将来的な排出量取引市場や炭素賦課金の導入を見越した投資の判断に有効です。ただし、外部向けに用いるには計算方法の透明性が課題であり、現在は試行錯誤の段階です。特にe-メタンやCCUSをどう扱うかで国際的な財務インパクトは大きく変わります。エネルギー業界全体で、財務インパクトの算出根拠を明示し、保証やルールを整備することで、将来的にCO2削減量が金額に換算され、企業価値に反映される仕組みが構築されると考えます。
社外取締役としての視点
第三者の立場から、見えていないリスクの指摘や
非財務情報の数値化を通じて、企業価値向上を目指します。
Q. 社外取締役として、日頃どのような視点を重視しているのでしょうか。
来島監査等委員会設置会社への移行により、形式的な議案の審議が減る一方で、戦略やリスクに焦点を当てた議論を深める必要性が増しています。
私は、JR西日本の経営で事故対応を経験してきたことから、エネルギー事業という異業種でもリスクと組織文化の両面に着目し、見えていないリスクを指摘する視点を大切にし、経営の質を高める支援をしていきたいと考えています。単なる理論で終わるのではなく、「どの組織の力を使い、いつまでに、何をどうするか」といった実行力にまで踏み込む視点を持ち、会社の持つ力を引き出す役割を果たしていきたいと考えています。
梨岡私は、公認会計士として環境やサステナビリティに長く携わってきた経験を生かし、「非財務情報の数値化」を通じて、ステークホルダーとの建設的な対話を促進し企業価値向上に貢献したいと考えています。
近年は情報開示の義務化や審査の厳格化が進んでおり、第三者の視点から会社に貢献できる場面が増えてきました。当社グループの人材戦略については、男女問わず働きやすい環境の整備を進めたり、社内から女性取締役が誕生するには時間がかかりそうですが女性管理職の増加に向けて取り組むことは、労働生産性向上につながると考えています。定年延長や役職定年の廃止などのシニア活躍の取り組みも先進的です。今後、人的資本の数値化と活用が企業価値向上の鍵になると捉え、積極的に提言していきたいと考えています。
Q. 来島取締役の「見えていないリスク」とは具体的にどのようなリスクを想定していますか。
来島私が社外取締役に就任して以降、フリーポートLNG基地の事故や袖ケ浦バイオマス発電所の火災などの重大事象を経験しました。こうした事象に対し、どの部門がどう対応し、それをどのように教訓化し今後の行動につなげていくかを常に意識しています。ガス事業は事故の頻度こそ少ないものの、一度発生すれば影響が大きいため、被害を最小限に抑えるための予知と備えが重要と考えています。
Q. 梨岡取締役の「非財務情報の数値化」とは、どのように進むものと捉えていますか。
梨岡「非財務情報の数値化」は、私自身、環境会計を始めた頃から取り組んできたテーマです。企業の価値創造は経済価値と社会価値の両面から捉える必要がありますが、これまで社会価値は感覚的に語られ、比較や評価が難しいものでした。そこで、CO2や水、人的資本といった非財務資本を定量化し、信頼性のある指標として整備していくことが課題です。
例えば、かつてCO2の1トンあたりの価格は数百円から数万円まで幅広く評価されていましたが、近年は計算方法が整理され、保証に耐えられる水準に近づいています。今後は人的資本等も順次数値化が進むと考えます。企業は試行錯誤しながら価値創造にかかわる指標として数値情報を開示し、投資家の皆さまはそれを意思決定に利用していただくことが肝要です。私は、この動きを後押ししていきたいと考えています。
ダウンロード 統合報告書ダウンロード
- サステナビリティ
マネジメント -
推進体制
マテリアリティ
ステークホルダー
エンゲージメント 価値共創の歩み 価値創造プロセス
- E:環境
- E:環境
環境マネジメント
Daigasグループ環境方針
(参考情報)環境会計の
集計方法について バリューチェーンにおける
環境影響 環境目標 気候変動対策 (参考情報)CO2排出量
削減効果の評価 TCFD提言に基づく情報開示
-リスクと機会の認識と対応- 資源循環社会への貢献 (参考情報)
資源循環に関するデータ推移 (参考情報)土壌・地下水の
保全 調査結果公表リスト 生物多様性 Daigasグループ生物多様性方針 環境技術開発
- S:社会
- S:社会
イノベーション・マネジメント
DXによる事業変革/研究開発・知的財産/新規事業創出 人材マネジメント/人材戦略目標 人材育成 DE&I
(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン) Daigasグループ
ダイバーシティ推進方針 ワーク・ライフ・バランス 労働安全衛生 Daigasグループの健康経営 従業員と会社の
コミュニケーション 人権
バリューチェーンを通じた人権の尊重/人権デュー・ディリジェンス/人権啓発活動 Daigasグループ人権方針 サプライチェーン・マネジメント Daigasグループ調達方針 (参考情報)主なエネルギー
バリューチェーンが
社会に与える影響 顧客の安全衛生 顧客満足 コミュニティ
地域共創活動/公益財団活動
への取り組み 社外からの評価 イニシアチブ参加
- ESGデータ集
- 第三者検証 環境パフォーマンスデータ 社会データ ガバナンスデータ
- ガイドライン対照表
- GRIスタンダード対照表 SASB対照表 環境報告ガイドライン対照表 TCFD提言対照表
活動報告方針 レポートダウンロード アンケート トピックスバックナンバー サステナビリティ
サイトマップ

