トップコミットメント
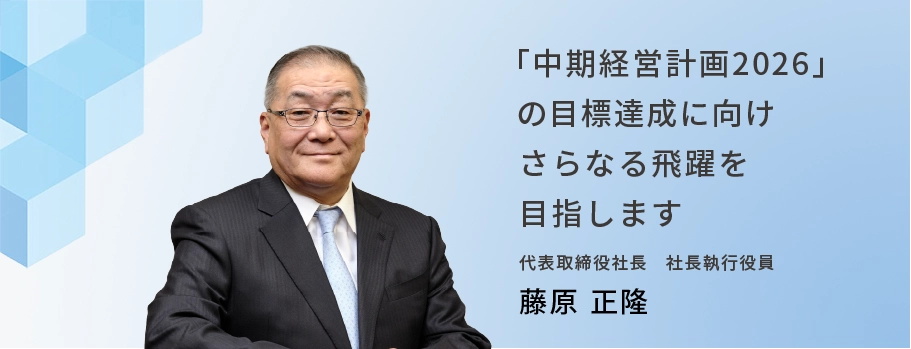
2024年度を振り返って
トランジション期における事業成長と未来への投資にバランスよく取り組む
2024年度は、国際的には地政学リスクが高まり、国内外でインフレが進むなど、政治・経済情勢の見通しが困難で不確実性の高い状況が続きました。そのような環境下においても、Daigasグループはトランジション期における事業成長と、未来への投資の両輪にバランスよく取り組んでまいりました。
トランジション期の成長としては、国内電力事業、米国サビン社を中心とした海外上流事業が伸長しました。また、トランジション期の現実的なエネルギーとして天然ガスへの期待が高まるなか、LNGの分散調達先の確保や、天然ガスへの燃料転換工事の提案等の取り組みを強化したことに加え、製造・供給部門では、自然災害等への対応を含む設備対策工事の実施など、エネルギーセキュリティを高める取り組みを計画的に進めることができました。
さらに、ライフ&ビジネスソリューション(LBS)事業でも、各社が培った強みと当社グループのシナジーを発揮しました。都市開発事業では環境・防災に優れた商品の提案や、材料事業では活性炭をはじめとした高付加価値な製品の開発・展開、情報事業では当社グループ内のDX推進を行うとともに、ERP※事業の拡大などにより、事業を着実に成長させました。
- ※ ERP: Enterprise Resource Planningの略。お客さまの企業活動を一元管理し、効率的な経営に寄与するシステムのこと
未来への投資としては、SOECメタネーションのラボスケール試験装置を完成させたほか、2030年度のe-メタン1%導入に向けた米国での製造プロジェクトの詳細検討を完了させるなど、e-メタンに関する技術開発を着実に進めました。また、成長市場のアジアでは、インドでの都市ガス事業の事業エリアの拡大など、将来の利益成長につながる投資を実施しています。
これらの活動の結果、2024年度の収益性指標は計画を上回る水準で達成し、将来への歩みを着実に進めることができた1年となりました。
日本を取り巻くエネルギー情勢の変化とその影響
「第7次エネルギー基本計画」で示された、天然ガス活用を含めた安定供給の重要性
国内エネルギーに関する大きなトピックスとしては、2025年2月18日、第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。新たな基本計画では、欧州・中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安全保障上の要請の高まりや、DXの進展に伴う電力需要増加など、国内外のエネルギー情勢の変化を踏まえ、エネルギー安定供給や脱炭素化に向けたエネルギー構造の転換を経済成長につなげるため、産業政策を一層強化する方向性が打ち出されました。また、先行きが不透明ななか、2040年時点で脱炭素技術の開発・革新が進まないリスクケースも想定され、LNGの長期契約の確保など、エネルギーの安定供給に万全を期すべく化石燃料の確保・活用がうたわれています。特に天然ガスは、化石燃料のなかでも温室効果ガスの排出が最も少ないことから、石炭などからの燃料転換を通じた天然ガスシフトの進展が環境負荷低減に寄与することも示されました。さらに、水素やアンモニア、e-メタン等は次世代エネルギーとして位置づけられ、国からの技術開発・設備投資支援の必要性についても言及されています。
「Daigasグループエネルギートランジション2050」の策定
カーボンニュートラルの社会実装をリードする
プレイヤーとして、多角的なソリューションで挑戦を続ける
第7次エネルギー基本計画で2040年の新たなエネルギーミックスの姿が示されたことにより、2050年に向けた国のカーボンニュートラル(以下、CN)のロードマップがより具体的になりました。そこで、総合エネルギー企業である当社グループとしても、2050年に向けた具体的な道筋を示す必要があると考え、2025年2月27日に「Daigasグループエネルギートランジション2050」を公表しました。
そのポイントは3つあります。まず一つ目は、当社グループが進めるエネルギートランジションの全体像として、2050年までのロードマップを、複数の想定シナリオで具体的に提示したことです。特に当社が見据える2040年の想定数値を示すことにより、CN化の道筋をさらに明確にしました。今後は事業環境の変化に応じて、これらのシナリオを随時見直す必要があると考えます。
二つ目は、当社グループが供給する電気・熱エネルギーのCN化だけでなく、ネガティブエミッションも含めた大きく3つの領域において、世のなかのCN化に貢献することを表明したことです。総合エネルギー企業として、お客さまのニーズに合わせた多様なエネルギーの選択肢をご提供しますが、特にe-メタンと再生可能エネルギー(以下、再エネ)を事業の柱として注力してまいります。e-メタンの最大のメリットは既存のインフラをそのまま利用できる点にあり、お客さまを諸々の手続きで煩わすことなく、シームレスにCN社会へ移行でき、燃料転換による社会コストを低減できます。
最後に三つ目は、お客さまとともに「ミライ価値」を共創していくための様々なソリューションを示したことです。当社グループは、当社が供給するエネルギーのCN化だけでなく、それをご利用いただくお客さまのお役に立つ、お客さまに寄り添ったソリューションをご提案することで、ともにCN社会の実現を目指して挑戦を続けてまいります。
「中期経営計画2026」で掲げた重点戦略の進捗
計画を着実に実行しつつ、新たな課題への対応に取り組む
メタネーション実証試験の実施、基本設計への移行など、エネルギーのCN化を着実に進める
「中期経営計画2026」では、重点的に取り組む活動を「3つの約束」として掲げており、着実に進捗しています。
一つ目は「ミライ価値の共創」です。エネルギーのCN化としては、SOECメタネーションの開発においてベンチスケール試験への移行を進めるほか、新潟県長岡市での大規模サバティエメタネーションや大阪・関西万博会場でのメタネーション実証実験に取り組んでいます。また、米国でのe-メタン製造プロジェクトは基本設計に移行します。電力については、日向・愛知田原バイオマス発電所の運転開始などにより、他社からの調達を含めた再エネの普及貢献量は2024年度に370万kWに達しました。FIT市場の縮小により、今後、太陽光発電の拡大は容易ではありませんが、一方で、生成AIの普及によりデータセンターなどでの電力需要は増加しており、当社グループが貢献できる余地はまだまだあると考えます。特定のお客さま向けに電力を直接販売するコーポレートPPAを軸に、再エネの上流から下流まで、即ち、電源開発から販売まで、強みを生かした活動を続け、2030年度に500万kWの達成を目指します。
お客さまの真の課題を見つけ、「三現主義」を実践
2024年度のお客さまアカウント数実績は1,071万件と、中期経営計画2026で掲げた目標の1,090万件に大きく近付きました。これは、当社グループの社是である「サービス第一」の精神を従業員一人ひとりが理解し、お客さまの潜在ニーズを捉え、それにお応えする商品を生み出し、ご提案した結果であると考えます。私も若い頃、工場への都市ガス営業を行っていましたが、製造現場に何度も足を運び、工場の製造プロセスを熟知するうちに、お客さまにとっては“当たり前”のこととして見過ごされていた省エネポイントに気づき、最適なシステムを提案することができた経験があります。私自身、従業員とコミュニケーションをとる際には、こうした経験談を交えながら、お客さまの真の課題を見つけようとする、いい意味の「おせっかい精神」や、現地・現物・現実を重視する「三現主義」の重要性を伝えるように心がけています。
従業員の成長環境を整備し、人材の確保と育成に一層強く取り組む
二つ目は、「従業員の輝き向上」です。近年、人材の流動化が顕著になり、当社グループでもキャリア採用が増え、世代や経歴などの面で、以前よりも多様性に富んだ従業員が各職場で専門性を発揮しています。大変、良いことだと思っています。
企業にとって、入社後の従業員が挑戦意欲を持ち続け、成長実感を得られるかどうかは最重要課題であると考えます。そのため、2024年度には、一人ひとりのキャリア形成支援策として、先輩社員の社内経歴を参照しながら上司との面談ができる「キャリアポータル」や、社内インターンシップ制度「イカスキル」、社内副業制度「タメスキル」などを開始しました。2025年度には、従業員の業績をタイムリーに評価して処遇に反映することで、より高い挑戦意欲や業績貢献につなげる仕組みや、定年年齢を65歳まで段階的に引き上げ、年齢に制約されない活躍を促す制度の導入など、従業員の「挑戦と成長」を後押しする環境整備を進めています。今後もグループの成長を支える人材の確保と育成に、より一層力を入れて取り組んでまいります。
家庭用部門で構築したDX推進体制を拡大し、グループ全体の事業変革を加速する
三つ目の「経営基盤の進化」については、DXによるビジネスモデルの変革を進めています。現在、家庭用部門において、事業部門とデジタル部門が一体となって事業変革を進めるDX推進体制の構築に取り組んでいます。お客さまデータを活用することで、従来のご家庭単位のサービス提案に代えて、同じご家庭であっても、お客さま一人ひとりに焦点を当て、最適なタイミングで最適なサービスのご提案ができるように、家庭用システムの再構築を進めています。今後、その対象を業務用・産業用部門、ネットワーク部門にも広げ、グループ全体の事業変革を加速いたします。
その他、2025年度に運転を開始する千里蓄電所でも、卸電力市場において、いつ、どのタイミングで放電・充電を行えば、売却・調達の差益を最大化できるかを自動計算する運転最適化システムの運用を開始します。
また、これらの活動を支えるDX中核スタッフ人材のさらなる増強にも取り組みます。
重点事項の監督強化と機動的な対応を実施し、
ガバナンスを強化できた一方で、コンプライアンスの再徹底が課題
2024年度は、重点事項についての監督機能の強化と機動的な意思決定に向けて、監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会では「中期経営計画2026」の重点戦略の執行状況やサステナビリティ指標※の進捗状況を監督するとともに、ROIC経営の推進、資本効率向上に向けた課題等についても議論しています。さらに、当社グループ全体にかかわる重要リスクに対する予防保全の取り組みを管理・監督するため、全社委員会である「リスク管理委員会」を設置しました。委員会では各重要リスクに対する予防保全計画を立案し、その進捗状況を一元的に管理することで、グループ全体のガバナンスの強化を図っています。
一方で、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」の販売において、景品表示法上の疑義がある表示を確認した件については、お客さまの信頼を裏切る行為となり、ステークホルダーの皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、消費者庁による調査に対し真摯に協力し、大阪ガスマーケティング(株)をはじめとして、当社グループ全体で再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス意識を再徹底し、信頼回復に努めます。
- ※ 2025年度に「ESG指標」から「サステナビリティ指標」へと名称を変更しました
2025年度の事業計画とその展望
最大の使命である「安全」と事業の進化を重ね、中期経営計画2026の目標達成を目指す
2025年度は、大阪ガスが1905年(明治38年)の創業から120年を迎える節目の年です。
 120周年記念ロゴ
120周年記念ロゴ2025年度も、新たな動きやチャレンジがあります。まずは、姫路天然ガス発電所の運転開始です。環境アセスメントを開始してから、およそ10年をかけた一大プロジェクトで、1号機が2026年1月、2号機が同年5月に運転を開始します。これにより、昨今の電力需要拡大に対応する大きな発電ポテンシャルが得られるので、当社グループの強みである電力バリューチェーンを生かしてビジネスの幅を広げてまいります。また、LNGタンクでのガス貯蔵、蓄電池での電力貯蔵を通じ、ガス・電力市場の最適化による利益機会の創出に努めます。
また、これまで開発・建設を進めてきた8つのバイオマス発電所が全て運転を開始します。安定的なFIT電源として合計規模は45万kWに達する計画で、当社グループは再エネ電力販売を通じてCN社会の実現に貢献してまいります。
さらには、e-メタンの実証プロジェクトが開始しています。先ほど申し上げたとおり、大阪・関西万博での実証実験や、新潟県長岡市での世界最大規模のサバティエメタネーションの運転を開始しています。
もちろん、当社グループの最大の使命、企業グループの根幹は安全・安心の確保とエネルギーの安定供給であることを忘れてはなりません。いくら先進的な取り組みをしようとも、保安・安全がおろそかになると、会社の屋台骨が揺らぐことになります。1995年の阪神・淡路大震災から30年が経ちましたが、設備投資などのハード面と、業務フローの改善や教育・訓練といったソフト面、これら両面での保安対策を継続・進化させてまいります。
こうした取り組みを進めるとともに、引き続き、環境や、人権などの社会、ガバナンスに配慮したサステナビリティ経営を着実に推進してまいります。当社グループでは、企業理念を実現するため、企業の姿勢を表明する「Daigasグループ企業行動憲章」や、役員・従業員が守るべき具体的な行動基準を定めた「Daigasグループ企業行動基準」を設けています。さらに、2007年、日本の公益企業として初めて「国連グローバル・コンパクト」への参加を表明し、企業が国際社会の良き一員として取り組むべき原則を支持しています。
「中期経営計画2026」の目標達成に向け、「今日の安心をまもり、未来の日常をつくる」という志を胸に、2025年度もさらなる飛躍を目指してまいります。
2025年7月
ダウンロード 統合報告書ダウンロード
- サステナビリティ
マネジメント -
推進体制
マテリアリティ
ステークホルダー
エンゲージメント 価値共創の歩み 価値創造プロセス
- E:環境
- E:環境
環境マネジメント
Daigasグループ環境方針
(参考情報)環境会計の
集計方法について バリューチェーンにおける
環境影響 環境目標 気候変動対策 (参考情報)CO2排出量
削減効果の評価 TCFD提言に基づく情報開示
-リスクと機会の認識と対応- 資源循環社会への貢献 (参考情報)
資源循環に関するデータ推移 (参考情報)土壌・地下水の
保全 調査結果公表リスト 生物多様性 Daigasグループ生物多様性方針 環境技術開発
- S:社会
- S:社会
イノベーション・マネジメント
DXによる事業変革/研究開発・知的財産/新規事業創出 人材マネジメント/人材戦略目標 人材育成 DE&I
(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン) Daigasグループ
ダイバーシティ推進方針 ワーク・ライフ・バランス 労働安全衛生 Daigasグループの健康経営 従業員と会社の
コミュニケーション 人権
バリューチェーンを通じた人権の尊重/人権デュー・ディリジェンス/人権啓発活動 Daigasグループ人権方針 サプライチェーン・マネジメント Daigasグループ調達方針 (参考情報)主なエネルギー
バリューチェーンが
社会に与える影響 顧客の安全衛生 顧客満足 コミュニティ
地域共創活動/公益財団活動
への取り組み 社外からの評価 イニシアチブ参加
- ESGデータ集
- 第三者検証 環境パフォーマンスデータ 社会データ ガバナンスデータ
- ガイドライン対照表
- GRIスタンダード対照表 SASB対照表 環境報告ガイドライン対照表 TCFD提言対照表
活動報告方針 レポートダウンロード アンケート トピックスバックナンバー サステナビリティ
サイトマップ

